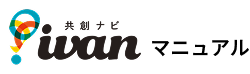あ〜お
ISO56000シリーズ
あいえすおーごろくまんしりーず
組織のイノベーション能力を体系的に強化するための包括的な国際規格。共創ナビivanの仕組みはこれに準拠している。
研究開発から市場展開までのイノベーションの全プロセスを効果的に管理し、持続可能な企業成長のフレームワークを提供する。
未来志向・柔軟性・価値創出に重きを置き、「守りのISO」とは異なる戦略的な標準。
IPランドスケープ
あいぴーらんどすけーぷ
技術分野や市場における知的財産(特許・実用新案・意匠など)の出願・登録動向を網羅的に可視化し、競合状況や技術トレンド、注力領域を分析する手法。
アーカイブ
あーかいぶ
過去の会議データを整理して保管すること。検討が済んだ会議をアーカイブすると、会議一覧が見やすくなる。
アーカイブされた会議は「アーカイブ一覧」からいつでも元に戻すことができる。不要になった場合は削除も可能。
アンゾフの成長マトリクス
あんぞふのせいちょうまとりくす
企業の成長戦略を「製品」と「市場」の軸で四象限に整理したフレームワーク。
事業開発を行う際には、市場浸透/製品開発/市場開拓/多角化のいずれかの戦略を選択する必要がある。新規事業開発においては、成長戦略をあらかじめ定義した上で検討するのが一般的。
イシュー
いしゅー
解決すべき課題や検討テーマのこと。事業開発においては、取り組むべき重要な論点や意思決定の対象を明確にするために設定される。問題意識の共有や優先順位付けを行う上で重要な概念。
イノベーション・マネジメント
いのべーしょん・まねじめんと
組織が継続的に新しい価値や事業を生み出すために、戦略的にイノベーション活動を管理・推進する手法や考え方。
国際規格「ISO56000シリーズ」などが代表的なガイドラインとして知られる。共創ナビivanはこの考え方に基づき設計されている。
OODAループ
うーだるーぷ
主に軍事戦略や意思決定に用いられる迅速な意思決定サイクル。
- Observe(観察):状況や環境の情報収集。
- Orient(状況判断):収集情報の解釈と自社・自分の立ち位置整理。
- Decide(意思決定):取るべき行動の選択。
- Act(実行):決定した行動の実行。
AIアシスタント
えーあいあしすたんと
共創ナビivanで用いられる生成AIの実行単位。
ボタンクリックのみで、あらかじめ設定されたプロンプトが実行され、市場データのリサーチ、アイデア生成、評価・フィードバックなどの結果が出力される。生成AIの出力に影響する情報を明確にするために、入力データ欄にはプロンプトで利用する入力フィールドやAI出力がリストアップされる。AIアシスタントはログイン利用者のみ実行可能であり、招待ユーザーは出力結果しか参照できない。
生成AIの出力に影響する情報が確認できる。出力結果をカスタマイズしたい場合は、カスタムプロンプト機能で独自設定が可能。
SSL/TLS
えすえすえる/てぃーえるえす
インターネット上の通信を暗号化する技術。共創ナビivanの通信はすべてSSL/TLSで保護されている。
SF思考
えすえふしこう
サイエンスフィクション的な視点から未来を構想するフレームワーク。
オープンイノベーション
おーぷんいのべーしょん
企業や組織が自社内だけでなく、外部の技術・アイデア・人材と協働しながら、新製品・サービスやビジネスモデルを創出するイノベーション手法。
か〜こ
会議
かいぎ
共創ナビivanでは、テーマを設定して一連のステップでアウトプットを出力するやりとりの単位を会議またはセッションと呼ぶ。
会議は目的に応じた「アプリ」が定義されている。
会議テーマ
かいぎてーま
会議名(セッション名)のこと。アプリ画面上部に表示される。会議作成時には「アプリ名+作成日時」が自動的に割り当てられる。
会議一覧には会議テーマが表示されるので、わかりやすい会議テーマを設定する。
カスタムプロンプト
かすたむぷろんぷと
共創ナビivan上でユーザーが独自にAIアシスタントを作成できる機能。独自の分析や出力結果を出したい場合に利用する。尚、カスタムプロンプトで作成したAIアシスタントはログインしたユーザーのみがその会議セッション上でのみ利用可能であり、別の会議セッションや別ユーザーとの共有はできない。
Gamma出力
がんましゅつりょく
Gammaとはプレゼンテーション、文書作成、ウェブサイト構築をAIの力で効率化する外部のAIツール。
共創ナビivanでは、AIアシスタントのエクスポート機能からGamma出力を選択することで、ivanの出力結果をGammaに転送してプレゼン資料を作成することができる。
機会探索
きかいたんさく
未知の市場や技術、顧客ニーズを幅広くリサーチし、潜在的なビジネスチャンスを発見するプロセス。
まだ顧客自身も気づいていない課題や価値の兆しを捉える。
技術シーズ起点
ぎじゅつしーずきてん
特許や知財など、自社の内的資産を活用して事業構想を検討するアプローチ。現在起点・内的資産起点の方向性。
QFT
きゅーえふてぃー
問いづくりのメソッド。Question Formulation Techniqueの略。多様な視点から問いを生成し、問い自体を改善することで課題の発見や仮説検証、行動の具体化を支援する手法。Right Question Instituteが提唱。共創ナビivanでは「探究/問いづくり」アプリで本プロセスが実装されている。
共創
きょうそう
企業や組織が顧客やパートナー、取引先、地域社会など多様なステークホルダーと「共に価値を生み出す」プロセス・手法。 Co-Creationとも言う。
共創相手はこれまでの人だけではなく、生成AIも共創相手になってきている。共創ナビivanは人と人の共創に加え、人とAIの共創を支援する。
Google Cloud
ぐーぐるくらうど
Googleが提供するクラウドサービス基盤。共創ナビivanはGoogle Cloud上で運用され、高い可用性と業界最高水準のセキュリティを確保している。
Google Patents
ぐーぐるぱてんと
Googleが提供する特許検索サービス。世界中の特許を番号やキーワードから検索・閲覧できるシステム。共創ナビivanでは「知財起点」アプリをはじめ特許検索機能ではGoogle Patentsをベースに行っている。
クロスSWOT分析
くろすすうぉっとぶんせき
SWOT分析で抽出した
- 強み(Strengths)
- 弱み(Weaknesses)
- 機会(Opportunities)
- 脅威(Threats)
を、互いに掛け合わせて4つの戦略を導き出す手法。
共創ナビivanの「SWOT分析」アプリではクロスSWOT分析が実装されている。
顧客課題起点
こきゃくかだいきてん
顧客が抱える課題やニーズから検討する、事業構想アプローチ。共創ナビivanでは「顧客起点」で採用されている。
コンセプトの検証(PoC)
こんせぷとのけんしょう(ぴーおーしー)
創出した事業アイデア(概要/ターゲット層/抱える課題/提供価値/解決策/目指す世界観)が市場ニーズに合致することを確かめるプロセス。Proof of Concept(PoC)とも言う。コンセプトの検証を通じて技術的実現性/市場受容性を評価して、リスクを低減する。
共創ナビivanでは評価指標をもとにした採点、探究/探索テーマを洗い出す問いづくり、アイデアのリスク分析/改善の支援が可能である。
コンセプトの創出
こんせぷとのそうしゅつ
イノベーションの種となるアイデアを体系的に生み出すプロセス。
アイデア概要、ターゲット層、抱える課題、提供価値、解決策、目指す世界観などを定義する。共創ナビivanでは顧客課題起点、技術起点、特許起点、未来起点、業界課題起点など多様なアプローチでイノベーションの種を創出する。
さ〜そ
サブメニュー
さぶめにゅー
共創ナビivanにおける作業エリア内の表示内容を切り替えるタブ形式のメニュー。クリックすると内容が切り替わる。ステップ進行と探究/探索などがある。
参加者(招待者)
さんかしゃ(しょうたいしゃ)
共創ナビivanのユーザー区分。ivan利用者から会議に招待され、参加するユーザー。参加者はAIアシスタント機能の参照とデータの入力のみが可能である。
視覚会議
しかくかいぎ
60分で合意形成を実現できる会議手法。ビジョンや方針をチームで握る、潜在課題を洗い出す場合に利用する。
バックキャストにおけるありたい未来の設定に有効。共創ナビivanでは視覚会議のファシリテーションを支援するアプリが利用可能。
自社アセット
じしゃあせっと
企業が保有する特許や技術、知的財産、ノウハウ、人材など、事業開発の起点として活用できる資産の総称。共創ナビivanでは会社名を入れるだけでWebリサーチにより強みや特徴を出力するAIアシスタントが実装されている。
収束AI
しゅうそくえーあい
企画書や報告書、評価の結論を生成するAIアシスタント。
1回の出力で1つの結論のみを提示し、意思決定や資料化を支援する。
生成要素には新規事業企画書、改善提案、行動計画、分析レポート、評価レポートなどが含まれる。
ジョブ理論
じょぶりろん
ジョブ理論(Jobs to Be Done 理論、JTBD理論)は、ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・クリステンセンらが提唱した顧客理解とイノベーションのための理論。
定義:人は製品やサービスそのものを買っているのではなく、「特定の状況で片づけたい用事(ジョブ)」を解決するために、それを“雇って”使っていると捉える考え方。
ジョブ(用事) = 顧客が達成したい進歩や解決したい課題。製品・サービス = そのジョブを片づけるために「雇われる手段」。
視点の転換 = 「顧客は誰か」「どんな属性か」よりも、「顧客がどんなジョブを解決しようとしているか」に注目する。
共創ナビivanでは顧客起点で事業開発を行う「顧客起点」アプリでジョブ理論をベースにしたアプローチを採用している。
進行画面
しんこうがめん
作業エリアに表示される、会議の進行用画面。人が入力や操作を行い、AIが結果を表示する。
CPF(Customer Problem Fit)
しーぴーえふ(かすたまーぷろぶれむふぃっと)
顧客(Customer)が抱える課題(Problem)の存在や深刻度を検証し、「本当に解くべき顧客課題」があるか確かめるフェーズ。
課題の切迫度が低いと、いくら技術を駆使しても十分な価値を生み出せないため、まずはこの段階で顧客インタビューなどを通じた検証を行う。機会探索や機会発見で機会や課題を見つけた後に検証するフェーズと言い換えることもできる。
CPC分類コード
しーぴーしーぶんるいこーど
欧州特許庁(EPO)と米国特許商標庁(USPTO)が共同で運用する、特許文献を技術分野ごとに細かく分類する国際的体系。Google PatentsではCPC分類コードで特許分類を行っている。例として「G06F3/00」(コンピュータ操作)などで表される。
SWOT分析
すうぉっとぶんせき
組織や事業、プロジェクトの現状を内部環境と外部環境の視点から整理し、戦略立案に活用するフレームワーク。
Strengths(強み)/Weaknesses(弱み)/Opportunities(機会)/Threats(脅威)を洗い出す。
共創ナビivanでは、「SWOT分析」アプリで提供される。
SCAMPER
すきゃんぱー
7つの視点から既存のモノやサービスを変化させ、新しいアイデアを生み出す手法。
- 代用(Substitute)
- 結合(Combine)
- 応用(Adapt)
- 変更(Modify)
- 別用途(Put to another use)
- 削除(Eliminate)
- 逆転(Reverse)
共創ナビivanではアイデア発想支援[Idea-Bridge]などで採用されている。
ステップメニュー
すてっぷめにゅー
共創ナビivanで会議の進行手順を示すメニュー。現在のステップはオレンジで表示され、クリックで該当ステップへ移動できる。
ステークホルダー
すてーくほるだー
事業やプロジェクトの実施により影響を受ける、または影響を与えるすべての関係者のこと。具体的には顧客、従業員、株主、取引先、地域社会、行政などを指す。
3C分析
すりーしーぶんせき
顧客(Customer)/競合(Competitor)/自社(Company)の3つの視点から市場環境を分析する手法。
自社の立ち位置や戦略の方向性を定めるために用いる。
共創ナビivanでは「3C分析」アプリを提供している。
請求項
せいきゅうこう
特許出願書類の「特許請求の範囲」に記載される項目で、発明の技術的特徴を文章で定義し、特許権の保護範囲を示すもの。
要するに「この発明について、ここまでを独占的に守ってください」と国に請求する部分で、特許権の範囲を決める最も重要な記載。
独自請求項と従属請求項がある。
た〜と
大規模言語モデル(LLM)
だいきぼげんごもでる(えるえるえむ)
大量のテキストデータを学習し、人の言葉を理解したり文章を作ったりできるAIのことです。
共創ナビivanで利用しているChatGPTは、この仕組みを使って動いています。
ダッシュボード
だっしゅぼーど
共創ナビivanにログインした際に表示されるメイン画面。各会議やアプリへのアクセス、進行状況の確認ができる。
多要素認証(MFA)
たようそにんしょう(えむえふえー)
IDとパスワードに加えて、スマートフォンの認証アプリで発行されるワンタイムパスワードを用いてログインする仕組み。セキュリティ強度を高めるために推奨される。
共創ナビivanでは企業単位で多要素認証の設定をすることが可能である。
探究
たんきゅう
明確な問いを立て、仮説を立案→調査・実験→分析・考察→検証を繰り返し、“理解”や“解答”を深めるプロセス。
共創ナビivanでは問いづく支援アプリ「探究/問いづくり」や各アプリに探究/探索機能を実装し、AIと人との協働による事業開発を支援する。
探究学習
たんきゅうがくしゅう
学習者自身が問い(問題・疑問)を立て、情報収集・実験・調査・討論などを通じて答えや理解を深める学習手法。
2022年度から高等学校学習指導要領で「総合的な探究の時間」が新設されている。
探索
たんさく
未知の情報・課題・機会を能動的に探し出す活動。
市場動向や技術動向、顧客ニーズなどを幅広く調査・分析し、次の仮説形成やアイデア創出につなげる。
共創ナビivanでは問いづくりり支援アプリ「探究/問いづくり」や各アプリに探究/探索機能を実装し、AIと人との協働による事業開発を支援する。
単純な問題(Simple Problem)
たんじゅんなもんだい
問題種別の1つ。必要な情報や条件が揃っており、目指すゴールが明確な問題。
特性:要素数が少なく、因果関係が明確で再現性のある解法が存在する問題。算数の計算問題、マニュアル通りの機械操作。
他の問題種別としては、複雑な問題(Complex Problem)、厄介な問題(Wicked Problem)がある。
知的財産
ちてきざいさん
知的財産とは、アイデアや発明、デザイン、ブランド名など、頭で考えて生み出した価値あるものを「財産」として守る権利のこと。
知の深化
ちのしんか
すでに得られた知識や技術を活用・最適化し、付加価値を高めるプロセス。
既存製品・サービスの機能改善やコスト削減 / ノウハウの標準化・マニュアル化による再現性向上。業務効率化や業務改善などがこれにあたる。
知の探索
ちのたんさく
未知の領域で新たな知識や技術、アイデアを発掘するプロセス。
市場や技術動向のリサーチ、実証実験(PoC)/ 異分野連携やオープンイノベーションによる新規発想。
新規事業開発では知の探索が必要となる。
問いづくり
といづくり
探究学習的思考を促し、課題の本質を見極めることで、仮説立案・価値創出・対話の質を高めるためにおこなう。
生成AIを活用する際においても、問いを作る力が求められる。共創ナビivanでは「探究/問いづくり」アプリで問いづくりメソッドであるQFT手法を活用した問いづくりを行っている。
問いの焦点(Question Focus)
といのしょうてん(くえすちょんふぉーかす)
QFTにおいて、問いづくりを実施する時のお題。質問形式にしない、シンプル、明確な焦点をもつなどの設定ルールがある。
特許
とっきょ
特許とは、新しい発明をした人が、一定期間その発明を独占的に使えるように国が与える権利のこと。
特許群
とっきょぐん
特許群とは、特定の技術テーマに関して、主特許とその周辺技術や応用技術を含む、関連特許の集合体を指す。
特許番号
とっきょばんごう
審査を経て権利設定(登録)が認められたときに付与される番号。「特許第●●●●●号」(例:特許第6543210号)の形式。
特許第…号は日本特許庁での公示・登録の際の正式表記。
Google Patents 上での指定方法:登録済み(B種別)の例:JP6543210B2
独自請求項
どくじせいきゅうこう
特許請求の範囲において、発明の本質的特徴を単独で定義する請求項。
他の請求項に依存せず、それ自体で権利範囲を特定できる。
特許権の中心(コア)となる保護対象を規定する。
従属請求項
じゅうぞくせいきゅうこう
独立請求項または他の従属請求項を引用して、発明の追加的な特徴や限定事項を付加して定義する請求項。
引用元の請求項に記載された技術的事項をすべて含みつつ、さらに具体化・限定した形で権利範囲を規定する。
TRIZ
とりーずまたはとぅりーず
ソ連のアルトシュラーが提唱した、技術的問題を体系的かつ創造的に解決するための理論。
40の発明原理、進化の法則、9画面(マトリクス)分析などがある。
な〜の
9Windows
ないんうぃんどうず
システムを「時間軸(過去・現在・未来)」と「構造階層(超システム・システム・サブシステム)」の2軸で9つの視点に分けて俯瞰し、根本的な解決策や新たな発想を導く分析手法。共創ナビではアイデア発想支援[Idea-Bridge]で実装されている。
7つの機会
ななつのきかい
ピーター・F・ドラッカーが『イノベーションと企業家精神』で示した、ビジネスの機会を生む7つの視点。
- 予期せぬ成功・失敗
- 不一致・矛盾
- プロセスのニーズ
- 産業・市場構造の変化
- 人口構造の変化
- 認識の変化
- 新しい知識
は〜ほ
バイアス
ばいあす
無意識の偏りや先入観、固定観念のこと。業界や組織が長年の慣習や前提にとらわれることで、新たな機会や発想を見落とす原因となる。
共創ナビivanではバイアスを壊して事業開発を行うための様々な機能が実装されている。
バックキャスティング
ばっくきゃすてぃんぐ
ありたい未来の姿やゴールを先に設定し、そこから逆算して現時点からのステップや計画を考える手法。未来志向の戦略立案に役立つ。
共創ナビivanでは「未来起点」アプリで未来起点での問題解決を実装している。ありたい姿をチームで描きたい場合は、視覚会議手法がおすすめである。
発散AI
はっさんえーあい
検討条件やアイデアの候補を生成するAIアシスタント。1回の出力で複数の案を提示し、アイデアの発散を支援する。
生成要素には業界課題、バイアス、仮説、コンセプト、解決策、メリット、リスク、質問・アドバイスなどが含まれる。
PSF(Problem Solution Fit)
ぴーえすえふ(ぷろぶれむそりゅーしょんふぃっと)
顧客の課題に対して提示した“解決策”(Solution)が、実際に顧客に価値を提供できるかを検証する。
MVP をコンシェルジュ型で手作業提供するなどして、顧客がそのソリューションにお金を払うかを早期に確かめる。
PMF(Product Market Fit)
ぴーえむえふ(ぷろだくとまーけっとふぃっと)
製品がターゲット市場に受け入れられ、継続的な需要を獲得できる状態。
顧客のリピート率や口コミでの成長が見られ、事業として自走し始めたかを指標に測る。
PDCAサイクル
ぴーでぃーしーえーさいくる
継続的な業務改善や品質管理を行うための4段階プロセス。
- Plan(計画):目標設定と達成方法の策定。
- Do(実行):計画に基づく業務・施策の実施。
- Check(評価):実行結果をデータや指標で検証・分析。
- Act(改善):評価結果を踏まえてプロセスや計画を修正し、次サイクルへ反映。
ウォーターフロー型の開発モデルで採用されているプロセス。アジャイル型ではOODAループが採用されている。
PPCO
ぴーぴーしーおー
アイデアをブラッシュアップする手法。アイデアの良い点、懸念点を列挙して、打破策を検討する。
共創ナビivanでは「リスク検証/改善」アプリで実装されている。
ビジネスモデルキャンバス
びじねすもでるきゃんばす
事業の全体像を可視化し、要素ごとの関係性を整理するためのフレームワーク。
Human in the Loop
ひゅーまん・いん・ざ・るーぷ
AIの出力結果に対して人間が関与し、フィードバックや選択を行い、AIと人が共創するサイクル。高精度な意思決定を実現する仕組み。
評価AI
ひょうかえーあい
事業開発の専門家が用いる独自の評価指標に基づき、アイデアの事業性やリスクを数値化・可視化するAIアシスタント。
スコアが低い場合には生成条件を変更して改善することも可能で、独自の評価基準や足切りスコアを設定した意思決定も支援する。
共創ナビivanでは「リスク検証/改善」や「審査/評価」でアイデア評価機能が実装されている。
VUCA
ぶーか
変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字を取った経営環境の特徴を表す概念。
不確実性
ふかくじつせい
不確実性=“何が起こるか/どれだけ起こるか分からない”状態 → 測れない・管理できない。
複雑な問題(Complex Problem)
ふくざつなもんだい(こんぷれっくすぷろぶれむ)
題種別の1つ。必要な情報や条件は揃っていない、目指すゴールのコンセンサスが取れている問題
特性:要素や手順が多岐にわたり専門知識や分析が必要だが、最終的には最適解や手順化が可能な問題。
例:航空機の設計、大規模システムの構築。共創ナビivanでは探究/探索のための「探究/問いづくり」やリスク検討の「リスク検証/改善」などがおすすめである。
PEST分析
ぺすとぶんせき
政治(Political)/経済(Economic)/社会(Social)/技術(Technological)の4つの外部環境要因から、
市場や業界の変化を俯瞰する分析手法。長期的な事業戦略を考える際に活用される。
共創ナビivanでは「PEST分析」、「機会発見」で利用されている。
ま〜も
マーケット起点
まーけっときてん
市場の常識や業界バイアスを打破し、外的環境の視点から事業構想を検討するアプローチ。未来起点・外的環境起点の方向性。
未来ビジョン起点
みらいびじょんきてん
バックキャスト(ありたい未来像から逆算)して事業構想を検討するアプローチ。未来起点・内的資産起点の方向性。共創ナビivanでは「未来起点」アプリで実現している。
メトリック/測定指標
めとりっく(そくていしひょう)
事業活動やプロジェクト、業務プロセスのパフォーマンスを定量的に把握・評価するための「測定指標」のこと。
や〜よ
やっかいな問題(Wicked Problem)
やっかいなもんだい
問題種別の1つ。必要な情報や条件は揃っていない、目指すゴールのコンセンサスが取れていない問題。
特性:問題の定義自体があいまいで、関係者ごとに価値観や目標が異なり、明確な最終解が存在しない/見つからない問題。
例:気候変動対策、地域医療・福祉の課題解決。
バックキャストなど未来起点、ありたい姿起点で考えるのがおすすめ。共創ナビivanでは「未来起点」アプリが最適。
ら〜ろ
リスク
りすく
確率と影響がある程度想定できる状態 → 定量化・管理が可能。
両利きの経営
りょうききのけいえい
組織が「既存事業の効率化・最適化」と「新規事業の探索・創出」という相反する活動を同時に推進し、持続的な成長を図る経営手法。
わ〜ん
ワンタイムパスワード
わんたいむぱすわーど
認証アプリで一定時間ごとに発行される6桁の使い捨てパスワード。多要素認証の際に入力する。